この人に聞く!vol.26 小原流熊谷支部 山田紫映先生
山田 紫映先生
1994年5月一級家元教授取得
6つの学校に7つのサークル、ご自宅のお教室にこども教室、ボランティアでケアホームに花をいけるなど、山田先生の活動は多岐にわたります。
ご指導されている6つの学校は、どの華道部も活発に活動され、山田先生がご指導に入られてから、部員が10倍以上に増えた学校もあります。
学校で指導を始めるのはハードルが高そうですが、なぜ6つもの学校をご指導されるようになったのか、部員を増やす工夫などはあるのでしょうか。
明るく面倒見のよい山田紫映先生の魅力をご紹介します。

小原流との出会い
・先生といけばなの出会いについてお伺いさせてください。
お花との出会いは高校生の時です。
担任の先生のお姑さんが、小原流の先生だったんです。先生から、「お花もお茶も習えるからうちに遊びにいらっしゃい。」と言われて行きました。当時学級委員長をしていて、断りづらかったんです。(笑)
お姑さんは東京支部の新井愛仙先生でした。通うようになってから分かったのですが、この方は小原雲心先生に習われていて、埼玉県で初めて小原流の教室を開かれた方でした。新井先生に小原流と大日本茶道学会を両方習っていましたが、冬でも冷たい井戸水で手を洗ってからお稽古を始めないといけないなど、礼儀作法から叩き込まれました。先生はとても厳しくて辛かったのですが、当時は必死で習っていました。
ご自宅のお教室にはブリキの水盤がいくつもあり、小原流の初期の花器は沢山お持ちでしたね。それを使ってお稽古させていただきました。
その後、新井先生から関根玉富先生を紹介されて関根先生から指導を受けました。
花屋さんとのつきあい
・先生はお花屋さんに対して大切にしている思いがあるとお聞きしました。
恩師の関根先生に『花屋さんを育てるのも大事なこと』と教わりました。
現在5か所の花屋さんとのお付き合いがありますが、毎月挿花をお渡ししています。『小原流とはこんないけばなで、花材はこんな取り合わせをしています。』と学んでいただきます。そして、皆さんに「たてるかたち」を教えました。実際に小原流を体験していただくと、挿花を見た時に理解が深まるでしょう。
お花屋さんに足を運ぶと、お店に小原流でお花をいけてくださっているんです。手直しして差し上げると「綺麗になった!」と喜んで、もっと上手くなりたいと頑張ってくださいます。
関根先生の教えを守り、地域の花屋さんとは、密接な関係を築くようにしています。
近くに花卉栽培農家があるのですが、綺麗に咲いた花をトラクターで潰していたんです。ビックリしてお話を伺いました。花を咲かせても、市場に出せるのは3分の1程度であとは潰してしまうのだと。
指導している学校で、子供たちにも話しました。
「みんなは使わなかった花材を捨てているけど、みんなの手にした花材は選ばれてきた花たちなんだよ。選ばれなかった花はつぶされちゃったんだよ。もし自分が花で、選ばれなかったらどうする?」って。みんな「捨てられるなんて嫌だ!」と言って、それから自分の花材は、残った花材も全て持ち帰るようになりました。残った花材でも小さくいけられることも教えたので、家でも工夫して楽しんでいるようです。
コンポスト(堆肥をつくる容器(composter))を使用している学校もあります。おけいこの切った残り物を肥料にして、学校の草木にまいています。 コンポストの公式ホームページはこちらから
コンポストの公式ホームページはこちらから
中国の方々への日本文化紹介
2019年に、「中国から外交官など20人くらい来日するので日本文化のおもてなしをしたい。協力してもらえないか。」というお話を知人からいただきました。
私はお花とお茶を両方しておりますので、お迎えする花と、お食事の後に出すお茶を担当しました。
会場が熊谷ガーデンパレス(ホテル)だったのですが、花器やお茶の道具はすべて私の自宅にあったものを持ってきて使いました。皆さま方にはとても喜こんでいただき、おもてなしに使うことが出来て良かったです。
また、中国の方に日本をもっと知って欲しくて、おひなさまや兜、破魔矢なども自宅から運び、通路に飾りました。皆さん「すばらしい!」と感激してくださり、花やおひなさま、兜など全てと一緒に写真撮影をされていました。
中国の方がイベントの様子をビデオに撮っていたのですが、日本に訪日したメンバーだけで見るのはもったいないということになり、中国の色々な場所で皆さんに見ていただいたそうです。後日中国の方からわざわざお礼の言葉をいただいて、私も感激しました。
花はしばらくホテルにも飾りましたので、ホテルの方にもとても喜ばれました。

学校での指導
・現在6校をご指導されていますが、最初のきっかけとご指導される学校が増えていったお話を聞かせてください。
最初はボランティアで学校にいけていたんです。その学校の先生に声をかけていただいて教えることになりました。
子供だからといって、いい加減にならないように、とにかく丁寧に丁寧にと、子供の気持ちになって分かりやすいように心くばりをして指導しました。それを続けていたら、先生はきちんと見ていてくださったんですね。他の学校の先生に話してくださり、その学校から指導して欲しいと連絡が来ました。

公立の学校の先生は、転勤で県内の学校を移動します。指導していた学校の先生が移動し、学校に華道部がなければ作って「山田先生に来て欲しい。」ということもありました。その学校が小原流でなかった時は、小原流に変更して呼んでいただいたりもしました。
長く続けていますので、自宅教室の教え子が教員となって教えに来て欲しいと頼まれることもあります。その学校には現在も指導に通っています。
有難いことに自分から学校に働きかけたことはなく、学校の先生方からお話をいただいて増えていったんです。現在も、子供だからといって指導に手は抜かない、丁寧に、そえれぞれの子供をよく見てその子にあった指導をするということを続けています。
・学校で部員が30名を超える学校がいくつもありますが、部員が増えて時のエピソードがあったら教えてください。
体験教室を開催したことが大きいと思います。
このチラシを配り体験教室を開催したことで、部員が驚くほど増えました。
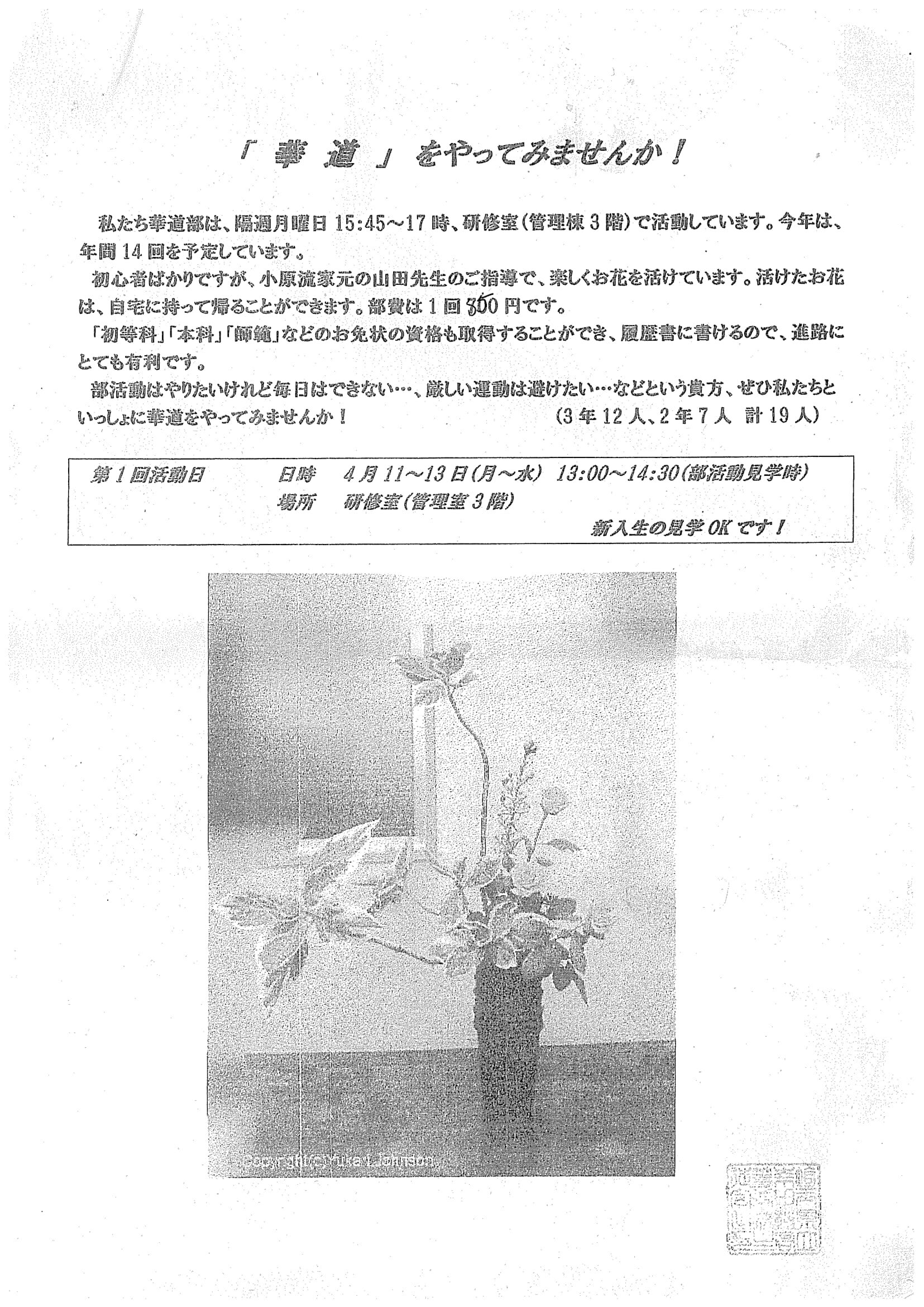
体験教室では、全員にミニブーケと紙コップにオアシスを入れて配り、簡単な「たてるかたち」を体験してもらったんです。
全てのお教室でいけばな体験をしたら、33人の新入部員が入部しました。実は50人くらい希望者が来てしまったんです。さすがにそんな人数は教室に入れないし、教えるのも大変すぎる!と33人にしてもらいました。
他の学校ですが、「楽しそうだから、どうしても入部したい!」と入部希望者が減らなかったので、2部制にしている学校もあります。30分交代で20人ずつがいけています。こちらの学校でも断ったお子さんもいるので心苦しいのですが仕方ありません。
今は私立志向になっているので、公立の学校では生徒獲得のために色々考えておられます。ある学校の華道部では、高校生が先生役になって、中学生を招いていけばな体験を年に3回くらいしています。
いくつものバケツに枝物、色別に花を用意して、器も紙コップやかごなど色々用意します。中学生の子は、バイキング方式に好きな花材を取り高校生に教えてもらいながらいけていきます。残ったお花はブーケにして、来てくれた中学生にすべて差し上げています。
このイベントをするようになってから、高校に入って華道部に入部する子がとても増えました。現在この学校の華道部も30名以上が所属しています。

華道部ではなく、普通の教室に花をいけておいて、生徒に枯らさないように見てあげてね。とお願いしたりもします。水がないと花は枯れるということも実際に体験して学んでもらいたいからです。
生徒さんたちには、「綺麗だな。好きだな。」と思ったら持って帰ってもいいよ。と話しています。とにかくお花を好きになってもらいたいと思っています。
学校の生徒さんの多くが許状申請してくださいます。
生徒さんの方が、「せっかく習っているのに、申請しないなんて考えられないよ。」と言ってきます。将来が楽しみな子ばかりで嬉しくなります。
・教え子が教員となった学校に、現在もご指導に通われているのですね。
はい。男性で華道部顧問をしています。
研究会にも出ていますし、将来は私の後を継いでいって欲しいなと思っているのですが、なかなかうんと言ってくれません。(笑)
顧問が良いと生徒が増えるんです。この学校は顧問が人気の先生で部員も多く、生徒もやる気で、いけばな競技会でも上位を目指して頑張っています。
サークル・こども教室などの活動
・こども教室もされているのですね。
子供たちにも長く教えています。子供が習っていると、お子さんのお母さまたちも習い始めますね。こども教室が終了すると自宅の教室に続けて来てくれる子が多く嬉しいです。
サークルはだんだんと人数は少なくなっていますが、楽しみにされている方ばかりなので続けています。
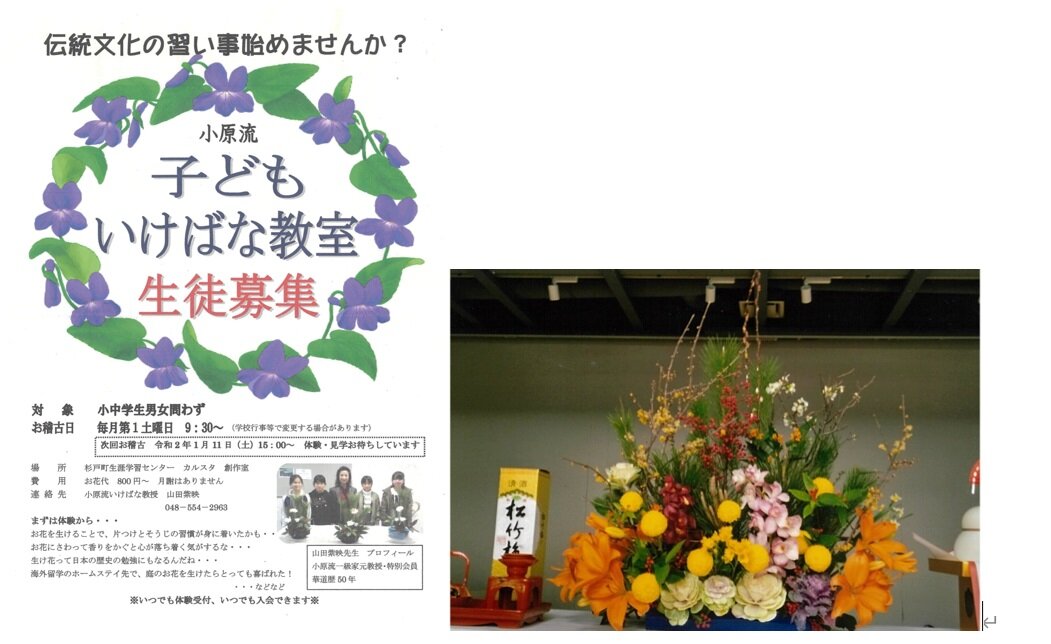
ケアホームにはボランティアで花をいけています。
いけていると、お年寄りの方たちが集まってきて「綺麗、綺麗。」と、とても喜んでくれます。
皆さん本当に喜んでくれるので、こちらまで嬉しくなります。花は人を元気にしますよね。
これから
実は去年の今頃、主人の体調が悪かったこともあって辛くなり、『お花を辞めてしまおうかな』と思った時があったんです。でも、いけばなが私の支えになりました。お花と小原流の仲間が私を励ましてくれたんです。いけばながあったことで、落ち込んでいた気持ちを立て直すことが出来ました。
小原流の仲間にも感謝しています。
私は人が喜んでいるのを見るのが大好きなんです。とても嬉しくなります。だから、『こうすれば相手が喜んでくれるかもしれない。』と思いながら、お花屋さんや生徒さんにも接しています。
私の大好きないけばなを、お花の魅力を多くの方に知ってもらうためにも、頑張らなくっちゃと思っています。
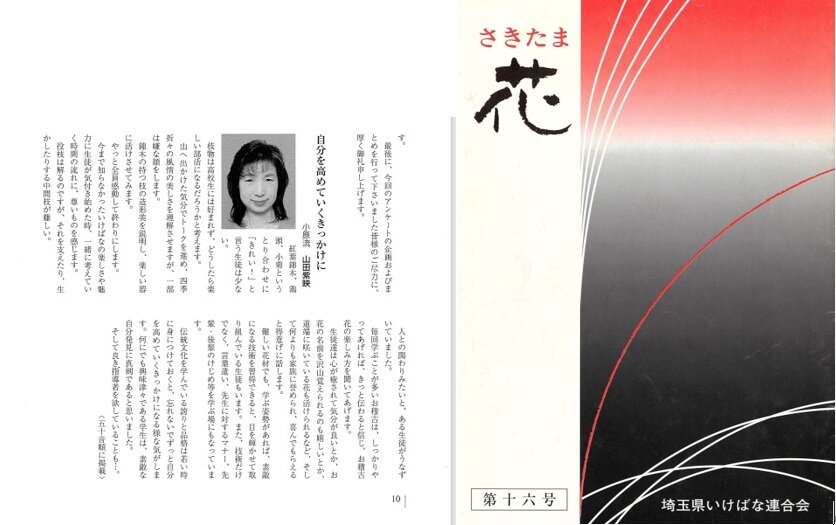
今回ご紹介した山田先生は、学生を指導する時でも子ども扱いすることなく、相手がどんな事を望んでいるか真剣に考えて丁寧に指導されています。
先生とお話していて『小原流をしっかり学びつつも、自由に楽しくいけてもらいたい。』と、生徒の気持ちを大切にする思いが伝わってきました。
本当はそろそろ引退したいのにね。とおっしゃいますが、沢山の生徒さんに慕われて、これからも生徒さんは増えそうです。まだまだご活躍を期待しております。
小原流では各種PRツールをご用意しております。
パンフレットもこちらからお申込みいただけます。
生徒募集のチラシも会員支援課でお作りできますのでご検討ください。
また会員支援課では「いけばなを習いたい。」とお問い合わせがあった方を、ご希望の地区の先生にご紹介させていただいております。
教室登録をされていない方は、ぜひ教室登録をお願いいたします。
教室登録はこちらから